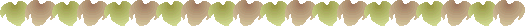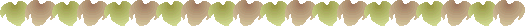
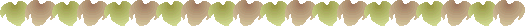
2004 年 6 月のある日、A4 版に印刷したプログラムを読んでいて、
中心部の文字がぼけていることに気づきました。
左右の目をそれぞれふさいでみたら、左目に問題があることがわかり、
すぐ近所の目医者さんに行きました。
「網膜の中心部の最もよく見える部分(黄斑)に穴があいています。
手術で直るけれど、かなり大変な手術です」と言われ、目の前が暗くなりました。
これがはじめて黄斑円孔という病気との出会いです。
老化による病気の1つだそうです。
眼球を球形にたもっている硝子体には、ゼリー状のものがはいっていますが、
年とともに変質して水のようになり、後ろの網膜との間が遊離してくるのですが、
硝子体の外側の膜と網膜がぴったりしていると、
網膜がひっぱられて破れ、穴があいてしまいます。
これが黄斑円孔です。
近眼の人がなりやすいそうです。
黄斑円孔の説明は
群馬大学の眼科の先生のページ
を参考にしてください。
私は近眼でめがねを使っていますが、矯正するとそれぞれ 1.0 は見えていたのですが、 この時左目は 0.4 位でした。 見ようとする部分がよく見えないというのが、この病気の特徴です。
病院の先生から手術のあらましをお聞きましたが、 術後のうつ伏せ寝が大事であることを強調されました。
インターネットで 「黄斑円孔治療体験記」を読み、いろいろ想像しました。 これを読んでいたおかげで、落ち着いて手術を受けることができたので、 是非私も体験談を書こうと思いました。
手術を受ける前には、今の視力がどれほどかを細かく記録しておくとよいです。 手術後どれほどよくなっているのかを知る手がかりになりますから。
目は 2cm 位の小さな器官ですが、これをとうして私たちは世界中を見ています。 この病気になって、目のありがたさと大切さをつくづく思いしらされました。
黄斑になんらかの問題があるかを調べる簡単な方法があります。
|
右の図を片方の目だけで中心の白い点を見ます。
私の場合、左目で見ると縦横の線ががたがたに曲がって見えます。 中心部は黒くなっていて、中心の白い点はみえませんでした。 手術後、線のがたがたは前よりは良くなりましたが、あいかわらず直線にはみえません。 右目との見え具合もかなり差があります。 |
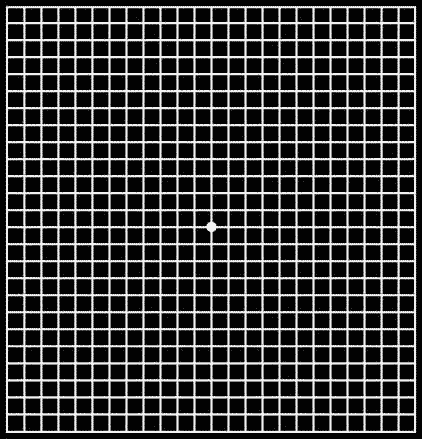 |
網膜剥離の原因となることがあるということで、100発くらいレーザー治療をして、網膜を固定しました。
15分くらいですが、かなり強い圧力を目に感じました。
治療後は出血で視界がややピンク色にみえるように感じました。
この治療の2週間後以降に手術ができるようになるそうです。
手術は、横浜市南部病院でうけました。 主治医は磯部先生、手術の担当医は米本先生でした。 細かい手術で大変だったことなど考えると、感謝の気持ちでいっぱいです。
手術は 2004 年7月21日9時から12時まで、約3時間かかりました。 時間ごとの経過を書きます。
| 06:00 | いろいろな目薬を1時間ごとにさす。 |
|---|---|
| 09:00〜 11:40 |
手術着に着替えてストレッチャ上で筋肉注射をして、4Fの中央手術室へ。 顕微鏡がある手術台の下へ移動する。 心電図、血圧、酸素吸入、左腕には点滴をつけ、 目のまわりを消毒し、左目だけを布から出し、いよいよ手術がはじまる。 磯部先生が首に局部麻酔をすると、フワッーとした気分になる。 この先は想像。 水晶体吸引が完了すると、いよいよ網膜と硝子体膜をはがす手術となり、 米本先生の声がきこえる。 右腕の血圧計が5分おきに作動している。 また左目は開いたままなので、水がいつも滴下している。 目の淵にくると痛みがあり、小さくうなる。 たぶん膜のくもの糸のようなものをすこしづつはがしているのだろう。 その後、ガスの注入がはじまり、少しづつ入れている。 だんだん目が膨らんでくる感じがした。 部屋のライトを消し、先生が網膜を一周確認したような感じだった。 そのあと、ライトを付け人工レンズを糸で固定した。 先生が「早く、早く、早く」と言って緊張した空気がながれ、 すごい勢いで終了処理に入った。 レンズが入るかどうかがとても心配だったので、うまくいったのかなと感じた。 手術室で移動用ベッドに移った時、先生にお礼をする。 この瞬間からうつ伏せ寝が始まった。 その後病室の移動用ベットがくるまで少しまった。 看護婦さんに「レンズははいりましたか」と聞いたら、 入ったとのことで安心した。 |
| 11:45 | 病室に戻る。少し昼食と水分を取る。 うつ伏せ寝用のまくらと胸当てがあり、 そのうえに体をあずけてうとうとするが、熟睡するまでにはならない。 クラビット点眼液、リンデロン液、ミドリンP を1日4回点眼する。 |
| 6/26 | 中心部の文字がぼけていることに気づき、近所の目医者さんに行って、 黄斑円孔という病気であることを知りました。ここで南部病院を紹介されました。 |
|---|---|
| 6/29 | 南部病院で黄斑円孔の手術のあらましをお聞きました。 また黄斑円孔の手術の前に網膜を固定するためレーザ治療を受けました。 この時の左目の視力は矯正して 0.4 でした。 |
| 7/20 | 手術のため午前中に入院しました。 |
| 7/21 | 手術当日:9:00 より 12:00 まで手術。 その後は、ベッドの上でうつ伏せ寝。音楽やラジオを聴く以外することがありません。 |
| 7/28 | まぶたのはれが、少しずつひいてきました。 ガラス体の水位が真ん中より上になりました。 頭をゆらすと、水面がゆれるのが見えます。なにか不思議な感じです。 |
| 8/2 | まる2週間たって、ほとんど硝子体は体液でうまった。 米本先生の診察があり、うつ伏せ寝をしなくてよいとの指示をいただき、 とてもうれしかった。 しかし、2週間もうつ伏せ寝をしていたので、仰向けになってもよく眠れなかった。 |
| 8/3 12:55 | 目の中で小さくなった気泡がパチッとはじけてなくなった。感激の一瞬。 これで硝子体は体液で満たされた。 |
| 8/4 |
左眼黄斑円孔の手術後、網膜に黒い影が見るようになりました。
お医者さんは、網膜が血でにじんでいる状態で、数ヶ月で消えるといいますが、
左目で見える視界が全体に暗く細部がはっきり見えませんでした。
8を横にしたような形で魚のように見えます。ちょうど胴体と尻尾の連結部分が 円孔のあった部分で白くぬけていますが、円孔の一辺の10倍くらいの 大きさがあり、面積としては百倍くらいになり、画面の大部分を占めます。 手術前は本の一部が見えずらい状態でしたが、今は本の文字全体が読めません。 これが消えないことはないか大変不安でした。 確かに手術直後よりは、少しよくなっているように思いますが、 景色をみていても、像全体が右で見るより暗く見えます。 |
| 8/9 | 午前中に退院し、昼食を外で食べ、マーケットに行ったら、
普通の景色が鮮烈でした。 左目の視力は矯正して 0.3 でした。 |
| 10/16 |
目の中の魚とのお付き合いも長くなり、しだいに気にならなくなってきましたが、
本の字などは読めません。左目の視力は矯正して 0.4 でした。 また人工レンズにもしだいに慣れてきましたが、やはり違和感があります。 |
| 12/9 |
水晶体の後側の膜が白濁して光を通しにくくしているので、
レーザでここに数ミリの穴をあける治療をうける。 このあと目が重くかんじるようになった。 |
| 2005 1/7 |
飛蚊が目の中に2つもあらわれた。
今まではテレビの画面に映るニュースキャスターの顔がほとんど見えなかったが、 少し見えるようになってきました。 |
| 2/7 |
左目の視力は矯正して 0.5 でした。
このごろ細かいものも少しみえるようになってきました。
眼底はとてもきれいなので、これからもよくなる可能性があると先生に言われました。 |
| 7/21 | 手術から1年たって人工レンズにも慣れ、心配していたこともふっきれました。 最近見えがよくなってきたように思います。特に直線の屈折はかなり改善されました。 ただ期待したようには視力は回復せず、手術前とあまりかわりませんでした。 |
私のように目に障害がある人や50歳代より上の年代の人は、画面を読むことで目の疲労感を訴える人が多いです。 少しでも楽に読めるように工夫していただけると助かります。色指定などはスタイルシートで行うことで、一括管理できます。
2006年2月8日朝日新聞の夕刊にこんな記事がありました。
人工網膜「光」みえた
大阪大学医学部研究課の田野保雄教授、不二門尚教授らのグループが、 人工網膜チップを眼球の裏の網膜裏に埋め込み、電気を流すことで、 網膜が光を感じたときと同じ電気信号が視神経に伝達され、光として感じた。
チップの電極は網膜や視神経に直接は触れていないが、距離が近いため電気信号をやりとりできるのだそうです。 2010年ころの実用化をめざし、メガネなどにつけた小型カメラの画像信号を眼球裏のチップに伝える システムを開発する。 また、指の本数や字を見分けるためには、チップの電極を100個程度に増やす必要があるという。
人工網膜は、有効な治療法がない重度の網膜色素変性症や、加齢黄斑変性などへの応用が期待されます。
| 著者 | 本の名前 | 出版社 | 値段 | |
|---|---|---|---|---|
| 井上毅一 | 手術室の中は闇 | 講談社 | 1500 | |
| 安保徹 | 免疫革命 | 講談社インターナショナル | 1600 | |
| 池田光男 | 目の老いを考える | 平凡社 | 1500 | |
| 白土城照 | 目の病気がすべてわかる本 | 主婦と生活社 | 1100 | |
| 金井淳 | 疲れ目を治す本 | 主婦と生活社 | 1300 | |
| 渡辺春樹 | 蹄跡 ALS患者となった眼科医の手記 | 西田書店 | 2415 |
| ご質問は |